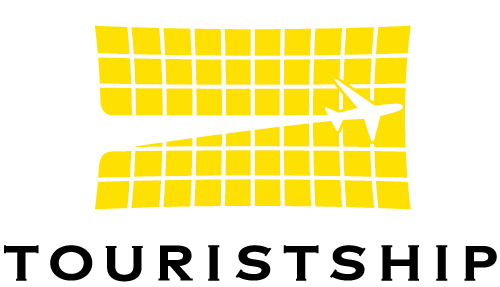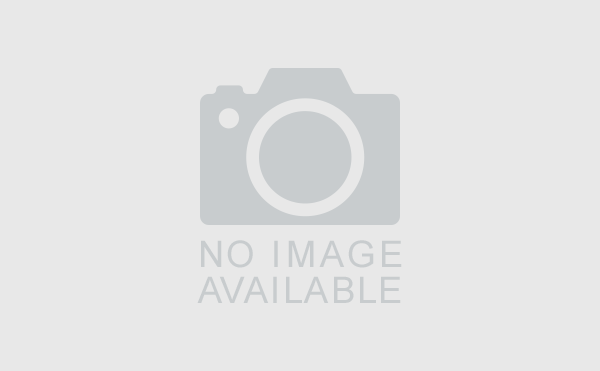Vol.015 三人でかいた汗、ツーリストシップ研究所とは何なのか
住宅街の中にある児童遊園に入る。そこで、本来は目立つはずの、子どもたちが無邪気に汗をかきながら楽しむ遊具よりも、圧倒的に目立つものに出逢う。
禁止事項に満たされた『ボールを使うな』『バットを持ち込むな』『自転車を乗り上げるな』『ゴミは持ち帰れ』の看板たちだ。
書いていることはごもっともだが、どこか他人事のような、俺が言ったわけじゃないけど的な、責任転嫁の集合体のようにも映った。大人たちがここまで禁止事項を鼓舞して子どもたちを制限しておいて、やれゲームのし過ぎ、YouTubeの見過ぎと、部屋にこもる子どもたちを、まるで知ったような口調で批判する。これだけ看板が増えたということは、大人と子どもの間に、大きな距離があるからだろう。つまり、大人たちの腰砕けが生み出した看板たちだ。昔は怖い近所のおじさんが、やかましいガキ大将を叱咤し追いかけ回したものだ。今はそんな大人たちはひっそりと鳴りを潜め、静かに役所にクレームをして、黙って看板を掲げる。自らの手を汚さず、全て丸くきれいに収めていくしたたかな大人たちに嫌気がさし、コスパだタイパだと騒ぎ立てる子どもたちのやるせない想いの方がむしろ私は理解できる。子どもたちの真価本領でもあった、純で、不器用で、無邪気な汗は、もはや児童遊園には、ない。だから子どもたちは、部屋に籠る。大人たちを、バカにする。ずらりと並ぶ看板たちをみて、思った。
先日、田中代表と井本ナレーターと小生の3人で、ツーリストシップ研究所をどうしていこうかと議論をした。誰に向けて、何について、どう広めようと話した瞬間、はたと違和感があった。
俺たちはそもそも、《広めようとしていたのか》ということだ。色んな展開を水平に伸ばすことは、この社団法人の根幹であることは言うに及ばずだ。もっと言えば、ここまでの水平展開は見ていても心躍る。いいぞ、もっと広げよう、もっと触れ合おう。このビジョンに間違いはない。
しかし研究所の役割は、その水平展開と決してイコールではなかった。いわば探究であり、試行錯誤であり、横ではなく縦に、垂直に伸ばし深めていくことであったはずだ。ただの善し悪しや効果の有無を推し量るものではなく、様々な論点や疑問、驚愕の見方や変わった視点も全て包含できる懐の深さを持ち合わせること。ツーリストシップ研究所とは何かという実直な問いでさえも、簡単に答えを引き出せないほどの気の遠くなる深さ、その垂直にそびえるポールに私たちの縁(よすが)があったのではないか、という気づきだった。
児童遊園に掲げられた看板たち。遊具以上に幅を利かせたあの水平展開は、どれも正しく、立派な意思だ。しかしそこに、汗は感じられない。オートメーションのような、無機質な言葉達だ。手を汚さない高みの見物は、ツーリストシップ研究所では許容したくない。いみじくも田中代表は、その議論の中で《汗》という言葉を何度も使った。汗が大事だ、汗を感じたいんだと。子どもたちの無邪気なハートは、その汗に集約されている。たくさんの出逢い、体験が、その汗を生み、やがて立派な大人になっていく。立派とは、己に垂直に立てたそのポールで生きていくということだ。安易で他人事な看板に、そんなマインドは皆無だ。
ツーリストシップ研究所は、これからも堂々と、その垂直を生き、何度もさ迷うことだろう。そのプロセスに、私は大きな希望を感じる。ぶさいくで、不器用で、馬鹿みたいに騒ぐ大人たちが、本当の意味で子どもたちを先導していく。看板なんてはぎ取ってしまえ。俺と会って話をしようじゃないか。一緒に、汗をかこうじゃないか。
そんな未来を、創りたい。