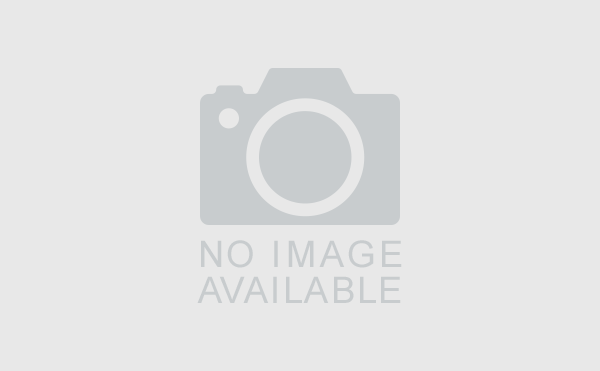Vol.021 ドバイが見せた「もう一つの観光の姿」
ヒアリングを終え、時計に目をやる。午前0時を回っていた。しかし自然と疲れはなかった。寝不足なまま田中代表のドバイの報告を聴き、そして質問を投げていくうちに時が過ぎていた。疲れが飛んでいく感覚、こういう不思議なことは、時折起こる。主訴たるものが沸き立った時、または論点が二転三転するスリリングな展開になると、疲労感が却って体に宿る血沸き肉躍る土壌になる。奇妙な話だ。
ドバイから帰国した直後に彼女は父親の出張先である青森に飛んでいる。観光立国の今を感じたまま、今度は父を訪ねての長旅を選択するのだから、なるほど、ツーリストシップを地で生きる人間の成せる業だ。
田中代表の話を聴いていて、ふいにある詩を思い出した。夭折の詩人・伊東静雄が遺した『そんなに凝視(みつ)めるな』である。
そんなに凝視(みつ)めるな わかい友
自然が与える暗示は
いかにそれが光耀(こうよう)にみちてゐようとも
凝視(みつ)めるふかい瞳には つひに悲しみだ
輝かしいものを凝視したとて、あるのはいつも、悲しみだという意味だろうか。一見するとネガティブな詩に聞こえるが、私にとっては希望だった。悲しみを真正面から受け止めることを認めてくれるような、そんな器を感じていた。どう感じ、何を考え、どのように事を起こすにせよ、そう、間違いを恐れず、悲しみを捉え、生きていく勇気への賛美にも聴こえた。
田中代表がドバイで感じた観光の現実は、決して自由さや開放的なものが溢れている実情ではなかった。ルール規制が存在し、管理監督の上で人々の生活や娯楽が営まれていく。日本人気質から見れば「何と不自由な事か」と敬遠されそうなエピソードも、ドバイでの観光を成り立たせる上ではきっと必要な事だったのだろう。その土地に、その地形が存在し、その地形によって生まれる自然や気候が、やがて人々の文化文明を創造していく。ジオパークの概念もきっとそこにあるのだろう。地質学と文化文明は切り離せない。ドバイにはドバイの背景があり、日本には日本の背景がある。
伊東静雄が凝視(みつ)めたであろう、「ついに悲しみだ」の下りには、きっとそこに立脚したものでしか語れない背景がある。その背景をなかったことにして、「本来の観光とはこうあるべきだ」と語ったところで、誰の胸にも響かない。異文化、異世界に立つということは、その悲しみ一つひとつに向き合うこと以外に許されないのではないだろうか。
電車内で居眠りをすると罰せられるドバイの規則。それは日本人の田中代表にとってどう映ったのか。違和感でもあり、だからこそ、その違いにも歩み寄ろうとした。難しく考えてみたり、それもありかと棚上げする田中代表の心の揺れを、私は聴きながら感じていた。「そんなに凝視(みつ)めるな 田中千恵子」と、伊東静雄が天から囁いたかどうかは、知らないが。
既にある状態と、一から構築していった状態の2種類がある。田中代表は日本とドバイの違いを、こうも表現した。地域色の違いに触れたかと思えば、最終的に「人が行動するにはどういう要素が必要なのか」という話題に及んだ。田中代表にとっての行動力とは「根拠のない自信」だと言い、私は「バカになることだ」と言ったら、互いに、うん納得、という感じだった。案外、やる前に想定していたリスクは起こらないものだ。絶対というものはないが、だからこそ歩みを止めずに、田中代表はここまで来た。ドバイの旅が田中代表を更に大きくした。旅というものは何だろうと改めて考察しているうちに、午前0時を過ぎていた。
『そんなに凝視(みつ)めるな』の結びはこうだ。
われ等は自然の多様と変化のうちにこそ育ち
あゝ 歓びと意志も亦(また)そこにあると知れ
自然が刻一刻と変化し、多様化する複雑な社会現象を生きる私たちに、ツーリストシップがこうして在る意味をもう一度“凝視(みつ)めてみる”。それは喜びを感じる事でもあり、悲しみを背負うことでもある。
深い夜の静けさとは裏腹に、疲れが体を鼓舞し始める。長い夜は、あっという間である。