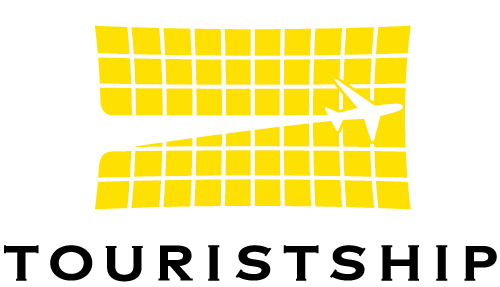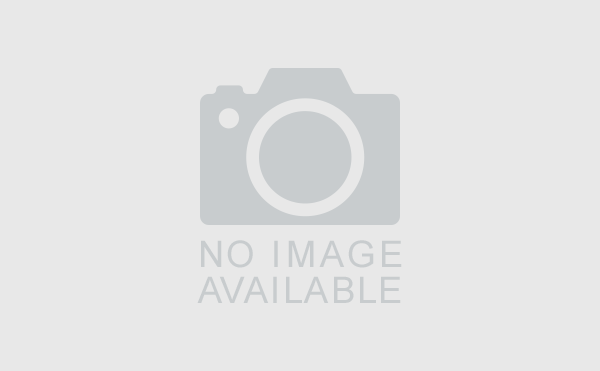Vol.025 へこみ、ふてね、おこり、きづき、つかれた。
いやー、ふて寝。
ただ寝たいだけ。
ほぼ1か月ぶりの「第一声」だ。というより、私が書いたメモの冒頭だ。
行動派も時には休む。揺れ動く感情、立ち現れる現実、その乱高下する波と戯れ、彼女は遂に、ふて寝を選んだ。
2度目の福島。そこで彼女は忘れられない書籍に出逢う。
小熊英二氏の『ゴーストタウンから死者は出ない』。その一節をご紹介する。
「被災地は大変です。一生懸命やっているが、自分のやっていることがどれだけみんなの役に立っているかわからない。」
ここで読み取るべきものがもしあるとすれば、「被災地は大変だ」という労いではなく、「なぜそんな想いに苛(さいなま)れるのか」という社会構造に対しての疑問符であろう。
職員の使命感や熱っ気とは裏腹に、その熱意を受け止める「計画性」に問題が生じている。この計画で出来るかどうかも分からないまま、職員の方々は目の前の人、そして課題に立ち向かっている。皆さんもご経験あるだろうか、せっかく熱心に作ったのに「ごめん、それもういらなかった」とか言われたときの衝撃。私だったら音まで聞こえる。がびーん、なのか、どどーん、なのか、それはその時々で違うだろうが、とりわけあの被災地での懸命な努力が計画性のなさによってもし不毛となれば、「どれだけみんなの役に立っているかわからない。」と吐露されても文句はいえまい。
つまりは、実感が持てない。
疲労感だけが募る、そしてやがて朽ち果てる構造なのだ。
この実態の欠乏が、彼女の心を打った。福島の現実を見た。
何とかしないといけない、こんなの、あってはならない、と。
ツーリストシップの普及に奔走するのは、まだ見ぬ観光客や住民の方々に、もっと本来の、楽しく意義ある社会を体感してもらいたい、否、もらう「べきだ」という強い意志だ。
福島の現状への違和感、行政を巻き込んでのロビー活動、その一つひとつが、本来のあるべき姿との乖離を原動力としていた。
彼女は「まだ」20代なのか、「もう」20代なのか。40代の私に言わせれば「まだまだ若い」となるのだろうが、社会の、そして世界の在り様から逆算すれば、「あとわずか」という形容しか合致しない。待ったなしだ。その上での、ふて寝、である。それほどのインパクトを、もたらしたのだろうか。
布団にくるまった時間は、それこそ数十分か一時間か、それくらいのことなんだろう(もちろん私はよく知らない)が、彼女の体感時計では3日間くらい寝続けてしまったくらいの「冬眠」である。
「被災地は大変です。」
言葉だけなぞれば、誰もが共感し納得する。しかし、ここに行き着くまでの道のりは、その場に立ったものでなければ、分かりっこない。簡単に納得されれば、それこそ福島が黙っていない。
それでも私たちは、何とか手を伸ばし、足を向け、その場に立ってみようと試みる。目を閉じ、心を冷やし、被災に遭った方々の鼓動を探る。しかしその度に、届かない自分の手足に、響かない自分の心に、冷ややかなものを感じ絶望する。でも、…それでも、…何か一つでもと、もがき、喘ぎ、そして、「ふて寝」する。この繰り返しは、確かに悲劇であり悲哀であるが、もしかするとそれさえも唯一の希望にするしかないのだろう。被災という体験を持たぬ私にとって、それしかできない無力さが光になる。無力であるということの実感と、その実感に立つからこそできる何かを「探すことができる」からだ。
実感が、持てない。
それは何も、あのコメントに託された当事者の想いだけではない。被災者ではない、それ以外の人の心にも、その言葉は十分なほどに内包される。実感の欠乏を静かに憂いでいる。実感が持てないということを、実感として持ち得ている。この強烈な現実を抱え、その狭間で、彼女は今日もツーリストシップを生き、笑顔で旅先クイズの旗を振る。
「へこみ、ふてね、おこり、きづき、つかれた。こんな感じですかね」
セッションの後半で言い放ったこの言葉は、シンプルにして深い。言うなれば人生、案外淡々と進むものだ。そのこともまた、田中代表は理解している。
この直後、今から別の方と打ち合わせしなければならなくなったと言って、電話が切れた。残された私の中で、今日のセッションの内容を整理しながら、改めて思ったことがある。
彼女は、実感を持ちながらも、実感に飢えている。その飢えが、彼女の心と体を駆動する。
被災地で奔走する方々と、共に生き、共に未来づくりを果たそうとしている。そのためのアクションを、「今も」し続けている。彼女は「もう」20代なのだ。
ふて寝していた人の行動とは到底、思えないほどの。