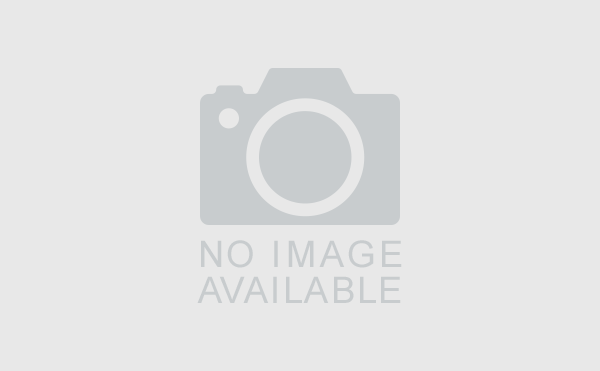vol.40 押しては返す波のように、ツーリストシップは発展する
もうここまで場慣れして「緊張しなくなった」田中代表が、なぜサミットで足が震えたのか。
サミットを終えた電話でのセッションは、この話でも持ちきりとなった。
いや、ちょっと違う。持ちきりだったというよりも、考えが割れた。
ちなみに田中代表の足を震えさせた緊張の原因は何か。それはサミット前日に、石垣島からお越しのミュージシャンの生演奏を聴いちゃったからだ。
ライブでしか感じ取れない生の音、臨場感、振る舞いが、田中代表の心を揺さぶった。心までは良かったが、翌日のサミットでその想いが増すあまり、足まで震え上がらせた。一ファンになってしまうと、どうしても我を忘れる。尊敬という想いが先行し、正常な進行を妨げる。公私混同はプロではない。その思いが田中代表をして「プロたるもの、律する心が大切」と言わしめた。そういえばWBCの決勝戦、日本対アメリカ。メジャーリーガー勢揃いのアメリカを前に、確かに大谷翔平選手は諭した。「今だけ、憧れるのはやめよう」と。だから優勝できた。田中代表の反省節が続いた。
だが私の意見は少し違っていた。ファンであるがために我を忘れ、公私が入り乱れる有様は、むしろ見せたほうがいいと思っている。できあがったもの以上に、想いが溢れるリアリティの説得力は絶大だからだ。だから反省など必要ないと言った。そういえば坂口安吾は『日本文化史観』で言っていた。美というものは、美を意識した途端に生まれてこないものだと。法隆寺が焼けても一向に困らぬと書いて、当時世間にどえらい印象を与えた。でも私は法隆寺は是非これからも焼けずに存在してもらいたいと思っている。
これは一体何の話や。こんな具合である。この掛け合いを続けていて思ったことがある。サミットでも恐らく、舞台と観客席との間で、様々な対話が展開されたに違いない。今後のツーリストシップの発展が、どれだけ多くのの国際問題を解決できるか、そのビジョンを最も鮮明に描いている田中代表たればこそ、あのサミットを成立させた。このリアリティには勝てない。そしてこれからも、このリアリティと共にツーリストシップは生きる。来年のサミットも8月6日、まだ内容は決まっていない。次回のサミットまでに、それこそ幾度となく繰り返すであろう、あーでもない、こーでもないという議論。そのプロセスこそが宝である。とんがったり、丸まったり、近づいたり、離れたり。まるで押しては返す波のように、ツーリストシップはこれからも意義あるプロセスを遺していく。
ところで田中代表にとって今回のサミットは、例年になく「楽させてもらった」そうだ。サポーターも増え、ますます馬力を増したツーリストシップである。そう思えば、胸きゅんでサミットに登壇したなんて話は、むしろ微笑ましい部類に入るではないか。事実、その余白ができたことで、田中代表もこうして俯瞰できた。胸キュンもできたわけである。
って、それこそ何の話や。…てな具合の、こういうプロセスも、あっていいのである。